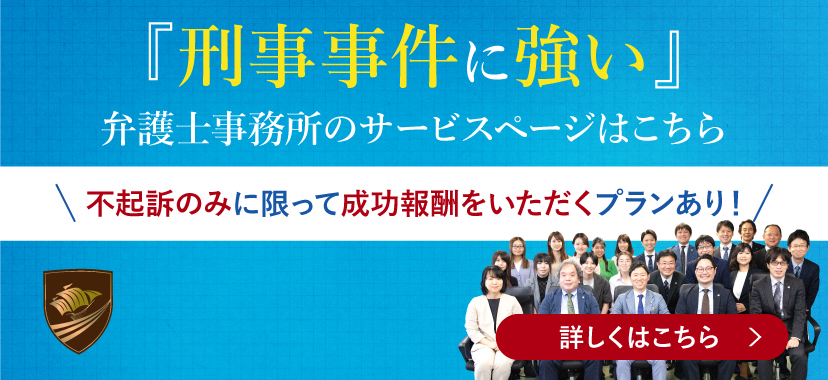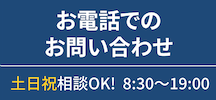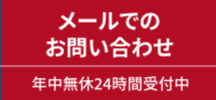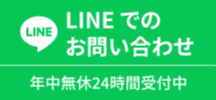被疑者、被告人の勾留中における弁護人の役割
被疑者や被告人にとって少しでも有利な結果が得られるよう、弁護士は勾留期間中に様々な刑事弁護を行います。
この記事では、起訴前の勾留と起訴後の勾留の違いについて述べた上で、それぞれの段階で弁護士が具体的にどのような活動を行うのかご説明します。
目次
1 被疑者(起訴前)の勾留と被告人(起訴後)の勾留について
勾留とは、証拠隠滅や逃走を防ぐために被疑者や被告人の身柄を拘置所や留置施設に拘束することをいいます。
なお、犯行の疑いがある人物のうち、起訴前の段階にある人のことを被疑者、起訴後の段階にある人のことを被告人といいます。
ここでは、被疑者の勾留と被告人の勾留について、それぞれの意味や期間の違いなどについてご説明します。
⑴起訴前の勾留とは
逮捕後、検察官は取り調べや捜査の内容などを踏まえて被疑者を起訴するかどうか判断します。
この間に被疑者の身柄拘束が必要だと判断されると、検察官によって勾留請求がなされます。
勾留請求がされると、裁判官が被疑者に勾留質問をし、勾留の必要性を判断します。
勾留が決定された場合、原則10日間身柄を拘束されます。
加えて、検察官が勾留延長請求をし、裁判官がこれを認めると、追加で最大10日間勾留延長がなされます。
⑵起訴後の勾留とは
起訴前の勾留の目的は証拠隠滅や逃走のリスクのなくすことでしたが、起訴後の勾留はこれに加え、被告人が公判に現れないという事態を避ける目的もあります。
起訴後の勾留には期間の定めがないのが特徴ですが、最初の裁判までの約2ヶ月程度の期間拘束されるのが普通です。
公判の回数が多くなるような事件では、裁判が終了するまでの期間が長くなります。
このような場合、検察が請求し裁判所が許可をすれば、1ヶ月ずつ勾留期間が延長されます。
2 被疑者の勾留中における弁護人の役割
被疑者が勾留されている期間、弁護士は不起訴や釈放を目指して次のような刑事弁護を行います。
⑴被害者との示談交渉をする
不起訴が得られれば、刑事裁判で何らかの罪に問われることがないので前科がつきません。
加えて被疑者の身柄も解放されます。
不起訴を得るためには、被害者との示談交渉を成立させることが重要です。
示談交渉が成立すると、当事者間での解決がなされたと判断され、情状酌量の余地があるとされる可能性があるためです。
なお、被害者との示談交渉ができるのは基本的に弁護士だけです。
示談交渉をする際は、警察や検察に問い合わせをして被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、加害者やそのご家族が連絡先を聞いても教えてもらえる見込みは高くありません。
スピーディーな解決を目指すためにも、示談交渉は弁護士に一任するべきでしょう。
⑵準抗告をする
勾留の決定に対する不服申し立て手続きのことを準抗告といいます。勾留をするためには、住所が定まっていないこと、証拠隠滅や逃走の恐れがあること、といった条件が必要です。
準抗告をする際は、これらの要件を満たしていないため、勾留するべきではないと主張します。具体的には、住所が定まっていることを主張したり、家族に身元引受書を書いてもらったりといった対応をします。
⑶勾留取消請求をする
勾留の決定が妥当であると認めた上で、現在は身柄拘束の必要性がなくなっていることを主張し、釈放を求めることを勾留取消請求といいます。
勾留取消請求を行うケースには、例えば次のようなものがあります。
| ・被害者との和解が成立しており、加害者にとって被害者に会いに行く動機がないとき
・捜査が進んでおり、隠滅するような証拠がもう残っていないようなとき |
⑷勾留延長の阻止をする
起訴前勾留の期間は原則10日間ですが、やむをえない事由がある際は勾留期間がさらに10日間延長されます。
検察官が裁判官に対して勾留延長請求をしますが、このとき弁護士が裁判官に勾留延長が適切ではないことを裁判官に主張することがあります。
主張が認められれば検察官による勾留延長請求が却下され、身柄が解放されます。
以上が被疑者段階の勾留時における弁護活動の内容になります。
不起訴を得られれば前科が付かないため、刑事事件では起訴をされる前に示談を成立させることが極めて重要です。
では、この間に不起訴が得られなかった場合、どのような弁護活動がなされるのでしょうか。以下で確認していきましょう。
3 被告人の勾留中における弁護人の役割
起訴後勾留の段階では、身柄の解放と執行猶予・減刑を目指して弁護活動をすることになります。
⑴保釈請求をする
起訴後の勾留はより長期間に及ぶため、日常生活への影響は計り知れません。
こうした不利益を軽減させるため、判決が出るまでの間一時的に身柄を解放する制度が保釈です。
保釈をするには、保釈金を支払う必要がありますが、裁判が終了すれば保釈金は返還されます。
被告人側から保釈請求があった場合、裁判官は原則これを認めなければなりませんが、必ず許可されるとは限りません。
保釈が認められるような申請書類を作成するためには、弁護士の力を借りるのがベターです。
⑵無罪を目指す(否認事件の場合)
被告人が犯行を行なっていない場合は、無罪を目指して弁護活動を行います。
無罪を目指す場合は、供述調書の内容をしっかり検討する必要があります。
供述調書の内容は刑事裁判で証拠として使用されるため、事実とは異なるような被告人にとって不利な供述がされていれば同意をするべきではありません。同意のない供述調書は証拠としての効力はありません。
また、無罪を獲得するためには証人尋問への対策が欠かせません。
刑事裁判では、有罪を立証するため、検察官が被害者や目撃者に対して証人尋問を行い、事件の様子について証言をしてもらいます。
これに対して、弁護士は被害者や目撃者などに対して反対尋問を行い、彼らの証言が事実とは異なるものであったと証明することを目指します。
⑶執行猶予や減刑を目指す(認め事件の場合)
一方で、犯行の事実を被告人が認めているケースであれば、有罪を受け入れつつも執行猶予や減刑を目指すことになります。
執行猶予とは、有罪判決が下ったとしても一定期間刑の執行を猶予することです。
この間に犯行を犯さなければ、刑は執行されません。
執行猶予を得るために、情状がよくなるような事情を集めていきます。
情状がよくなる事情は例えば…
| ・被害者と示談が成立しており、被害の弁済が済んでいること
・専門のクリニックに通っているなど、再犯防止に勤めていること ・贖罪寄付を行なっていること ・家族による支援が十分に期待できること |
ただし、次に当てはまるケースでは執行猶予は得られません。
| ・すでに執行猶予期間中である
・刑務所から出所して5年が経過していない ・懲役3年を超える刑を言い渡されている |
執行猶予が期待できないようなケースでは、減刑を目指して刑事弁護を行うことになります。
4 まとめ
この記事では、被疑者段階の勾留期間と被告人段階の勾留期間で、弁護士がどのような活動を行なっているのかご説明してきました。
刑事事件での弁護士の目的は、被疑者や被告人にとって少しでもいい結果を得ることです。
そのため、できれば起訴前の段階で被害者と示談交渉を成立させ、不起訴を獲得したいところです。
不起訴になれば前科はつきませんし、起訴後の勾留もありません。
今後の生活への悪影響を最小限に止めるためにも、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者

-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。