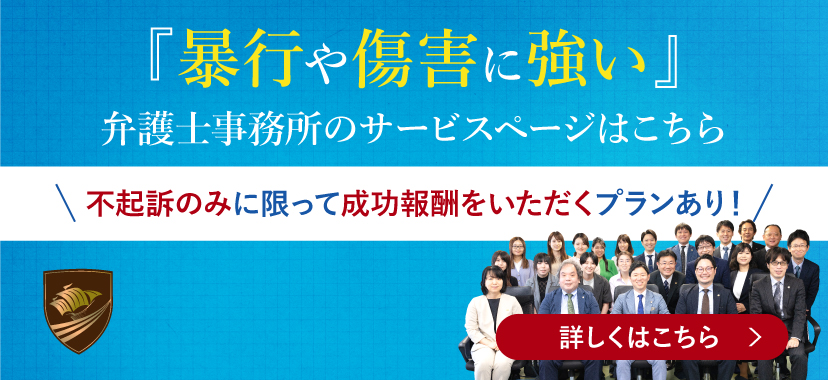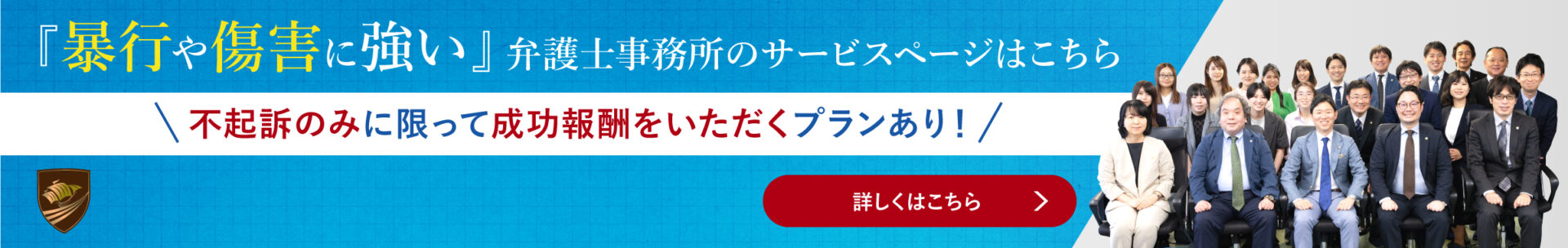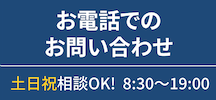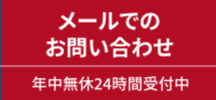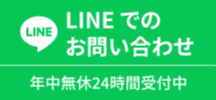こんな行為も傷害に該当する!早期の示談実現と不利益軽減のためには弁護士に相談
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金の刑罰を受けます(刑法204条)
傷害罪は、人の身体の安全を保護しています。
目次
1 傷害罪が成立するための要件
| ⑴「傷害した」といえる行為
⑵傷害の結果 ⑶行為と結果の間に因果関係があること ⑷傷害罪の故意 |
以下、事例に沿って説明します。
⑴「傷害した」といえる行為
| 事例①
Aは、ある居酒屋で友人のBに下痢をさせようとして、Bがよそ見をしている隙に、Bのビールにメチルアルコールを入れた。そのビールを飲んだ、Bは、疲労感、怠惰感を覚え、さらに下痢を起こした。 |
| 事例②
Cは弟Dと喧嘩して、Dの髪の毛を切り、とうとう坊主にしてしまった。 |
事例①でのAの行為は、Bの身体に向けた直接の有形力の行使ではありませんが、Bのビールにメチルアルコールを入れた行為により、疲労感、怠惰感を感じさせ、さらに下痢を起こさせたので、他人の身体の生理機能に障害を与え、または他人の健康状態を不良に変更させたといえ、傷害罪が成立します。
さらに事例②でCは、Dの髪の毛を切って坊主にしており、外見に変化をきたしてはいますが、他人の身体の生理機能に障害を与えたこと、または他人の健康状態を不良に変更させたといえないので傷害罪が成立しません。
これ以外にも具体的にどのようなものが他人の身体に傷害を与えたといえるか、以下、例をあげます。
| (肯定例)
・エイズに意図的に感染させる ・湖に落として失神させる ・いやがらせ電話でノイローゼにさせる ・ラジオ、目覚まし時計を大音量で長時間鳴らしてストレスを与えたことによる慢性頭痛症、睡眠障害を与える ・睡眠薬を与えて数時間にわたって意識障害を伴う急性薬物中毒症状 ・暴行・脅迫を加え「命が惜しければ指を歯でかんでつめろ」と命じ、被害者にその通りにさせた |
| (否定例、以下の場合は暴行罪)
・追いかけて転倒させる ・塩をふりかける ・太鼓を耳元で打って、朦朧とさせる ・狭い4畳半の室内で日本刀を振り回す |
⑵傷害の結果
髪の毛を1本抜いたり、小さな発赤は傷害にあたらないと一般に考えられています。
やはり傷害罪として処罰に値する一定程度の傷害結果が必要です。
裁判例を総合すると、全治4、5日程度以上のものに傷害罪が多く成立しています。
⑶行為と結果の間に因果関係があること
| 事例③
Eは、同僚Fをノイローゼにさせようと、数百回にわたりいたずら電話をしたが、気の強いFは、きっとEの仕業だと気づき、適当に相手にしただけで、ノイローゼになることはなかった。 |
「その行為がなければ、この結果は発生しなかった」という関係が必要です。
例えば、暴行行為により骨折の結果が生じたとされても、実はその骨折が別の原因によって負った負傷であることが判明した場合には、因果関係は否定され、傷害罪は成立しません。
事例③でのEの行為は傷害行為と言えますが、Fはノイローゼにならなかったため因果関係が否定されます。
そこで傷害未遂罪が成立するとも思えますが、傷害罪には未遂犯はなく、また、いたずら電話をかける行為は暴行罪にいう「暴行」にはあたりません。
したがって、Eには犯罪が成立しません。
⑷傷害罪の故意
| 事例④
Gは、友人Hにケガをさせるつもりで背中を押したところ、Hは、転んで怪我をした。 |
事例④のGは、Hに対して、傷害罪が成立します。
問題は、暴行するつもりはあったが、ケガをさせるつもりはなかったのに実際にはケガを負わせてしまったという場合です。
形式的にみると、傷害罪の故意が否定され、故意犯としては暴行罪止まりになるとも思われます。
しかし、実際に傷害結果を伴うような行為に出た場合に、暴行の故意と傷害の故意を明確に区別することは困難です。
そこで、刑法204条は故意犯としての傷害罪と結果的加重犯としての暴行致傷罪の複合型と理解するのが一般です。
判例も、上記のような場合にも傷害罪の成立を認めています。
事例④では、Iに対しては背中を押すだけ、つまり暴行の故意しかなかったのですが、結果的にIがケガをした以上、傷害罪が成立します。
2 傷害罪を犯してしまったら
ここまでは、傷害罪という犯罪自体の概要について説明してきました。
では、傷害罪で検挙されたとき、どのような手続きを受け、これに対して、どのように対処すればよいのでしょうか?
⑴逮捕から送検まで
逮捕された後、警察にて最長48時間、その後検察に事件が送致されて最大21時間にわたり身柄拘束された状態で検察官による取調べを受けます。
この勾留期間中に、検察は起訴あるいは不起訴するかの判断をします。
不起訴となった場合には、事件は検察限りで終了し、身柄は解放されます。
不起訴処分は前科ではありませんが、捜査対象になったという前歴は残ります。
⑵起訴・裁判・判決
起訴には略式起訴と公判請求があります。
略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する軽微な犯罪であること、被疑者に異議がないことが要件です。
略式起訴された場合は、検察庁で罰金を納付すれば、即時に釈放されます。なお、略式手続きは前科として記録されます。
公判請求された場合は、保釈制度により身柄拘束から解放されることもありますが、そのためには保証金が必要です。
その後、公判手続きを経て判決の言い渡しがなされます。
3 弁護士の役割
平成30年版犯罪白書によりますと、平成29年において傷害罪の検察庁既済事件数は約2万3千件、このうちの約56%の者が逮捕され(約1万3千人)、その約91%の者が検察庁に送検されています(約1万2千人)。
さらに、このうちの35%が起訴されています。そして、日本の刑事手続では起訴されると99,9%有罪となります。
ここで注目すべきは、60%以上もある起訴猶予(不起訴処分)率の高さです。
⑴起訴されるかどうかの判断基準
多くの要素が考えられますが、示談の成立の有無、傷害結果の重大性、犯行態様の悪質性、同種前科前歴の有無、反省の有無・程度等の事情を中心に判断されます。
このうち犯罪後に手を尽くせるのは、反省の態度と示談交渉です。とくに傷害罪は、身体の安全という個人の利益を保護することを目的としていますから、その個人が処罰をよしとしないと考えれば不起訴処分の可能性が高まります。反省の情を示す上でも、示談交渉は極めて重要です。
⑵示談交渉
刑罰に服しさえすれば法的責任を果たせるというわけではありません。
傷害罪の場合、被害者の治療費や慰謝料、さらに療養中働けなくなった場合にはその損失についても、民事上の責任が発生します。
そして、故意に他人に与えた損害に対する賠償責任は、たとえ破産したとしても免れ得ないことになっています。
裁判後、スムーズに社会復帰するためにも、あらかじめ示談交渉を行い、経済的な見通しを立てておくのが賢明と思われます。
もっとも、犯罪の当事者である加害者が、直接被害者のもとに出向いて円滑に交渉を進めることは現実的ではありません。
さらに、身柄を拘束されている場合には、そもそも出向くこともできません。
そこで、交渉のプロである弁護士が、被害感情を緩和させつつ、適切な内容・形式で示談を取りまとめ、その内容を意見書等とともに検察庁に提出し、不起訴処分に向けての働きかけを行います。
⑶示談の効果
示談の効果は不起訴処分に向けられたものだけではありません。
まず、示談の成立により、反省の情が認められ逃亡のおそれもないと判断されれば、逮捕そのものの必要性がなくなり、逮捕自体の回避が期待できます。
また、身柄拘束中であれば、その解放も可能となります。
逮捕後の勾留期間が長引くと社会生活に重大な影響を及ぼしかねず(失業、退学等)、たとえ、不起訴処分を受けたとしても、従来通りの生活が送れなくなるおそれがあります。
したがって、この時点で示談が成立していることが、その後の生活にとって重要となってきます。
そして、裁判後においても、適式な書面としての示談書があれば、その後のトラブルも防ぐことができます。
以上のようなことから、できるだけ早期に、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
4 まとめ
「酔った勢いで、つい」、「カッとなって」と誰しもが加害者になりかねない傷害罪ですが、その刑罰は重く、初犯であっても刑務所に入ることがあり、しかも、慰謝料も高額になる場合があります。早期の段階での示談を実現し、法的社会的不利益を少しでも軽減できるよう、弁護士がサポートします。
| 傷害の結果 | |||
|---|---|---|---|
| 発生 | 発生せず | ||
| 加害者の意図 | 傷害罪の故意 | 傷害罪 | 暴行罪 |
| 暴行罪の故意 | 傷害罪 | 暴行罪 | |
このコラムの監修者

-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。