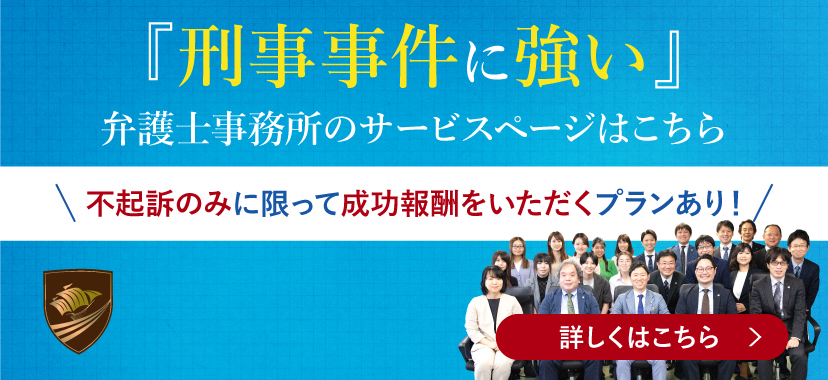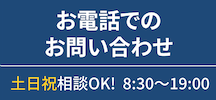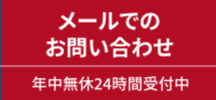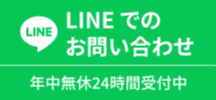刑法39条 責任能力の判断基準について
刑法39条には、「心神喪失者の行為は罰しない、心神耗弱者の行為は刑を減軽する」と規定されています。
心神喪失者、心神耗弱者とは、どのような人なのでしょうか?
こうした刑事責任能力は、どのようにして判断されるのかも一般にはあまり知られていないので、これを機会に知っておきましょう。
今回は、刑法39条の定める刑事責任能力について、解説します。
1 刑事責任能力とは
刑事責任能力とは、刑事罰を受けるに値する能力です。
判断能力がまったくない人や困難になっている人の場合、刑事罰を受けるだけの能力がないので、犯罪に該当する行為をしても、処罰を受けません。
刑法39条は、刑事責任能力のない、または少ない人として「心神喪失者」と「心神耗弱者」について定めています。
| 刑法39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 |
以下で、それぞれについて見てみましょう。
⑴心神喪失者とは
心神喪失者とは、自分が行う行為の善悪や是非の判断能力が完全に失われている人のことです。具体的には、重度の精神障害者や知的障害者の場合に心神喪失者と認められることが多いです。
心神喪失者の場合、刑事罰の対象外となるので、犯罪に該当する行為をしても、刑罰を受けることがありません。
⑵心神耗弱者とは
心神耗弱者とは、自分が行う行為の善悪や是非についての判断能力が著しく低下している人のことです。
やはり、精神障害者や知的障害者が該当することが多いですが、泥酔状態や薬物の影響などによって、ことの判別ができなくなっている場合にも心神耗弱状態と認定されるケースがあります。
2 責任能力を判定する方法
責任能力を判定する際には、「精神鑑定」を実施しますが、精神鑑定にはいくつかの種類があります。
⑴起訴前鑑定
起訴前に、検察官の判断によって実施される精神鑑定です。嘱託鑑定と簡易鑑定の2種類があります。
嘱託鑑定は、裁判所の許可を要する本格的な鑑定で、鑑定実施期間は勾留期間に含まれません。
簡易鑑定は、検察官の判断により、裁判所の許可なしに行われる簡易な鑑定で、鑑定実施期間は勾留期間に含まれます。
⑵公判鑑定
起訴後、公判段階になってから裁判所が実施する精神鑑定です。
⑶私的鑑定
被疑者の弁護人が自主的に実施する精神鑑定です。
私的鑑定の場合、当然には検察官や裁判所に提出されないので、有利な内容の場合、弁護人から検察官や裁判所へと提出する必要があります。
また、きちんと鑑定を実施するには、法医学に見識の深い精神科医による協力が不可欠となります。
3 具体的な事例
今までに、統合失調症の影響によって犯罪を犯した被告人において「心身喪失状態」が認めら、無罪となったケース(千葉地裁平成27年7月16日)、精神病による影響で子どもを殺したケースで心神耗弱による刑の減軽が認められたケース(東京地裁平成29年10月30日)などがあります。
以上のように、刑事責任無能力によって、刑の適用を避けられたり減軽してもらったりすることが可能です。お心当たりのある方は、一度刑事事件に専門的に取り組んでいる法律事務所ロイヤーズ・ハイの弁護士までご相談下さい。
このコラムの監修者

-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。